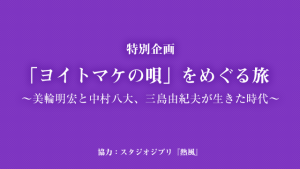新設された仏文科に転籍したことなどもあって、8年もかけて1965年の春に立教大学文学部を卒業したなかにし礼が歌謡曲の作詞家になったきっかけは、シャンソンの訳詩を依頼されたことだった。
タンゴ歌手だった菅原洋一は、その頃までにポリドールから6枚のレコードを出していたが、どれも全く売れていなかったので契約が切られる寸前にまで追い込まれていた。
なんとかラストチャンスをものにして、専属歌手にとどまろうと考えたスタッフたちは、シャンソンの「恋心」を越路吹雪と岸洋子がカヴァーすることを知った。そこで競作に持ち込むことで話題を盛り上げて、菅原洋一の知名度を上げる作戦を考え出したのは、ディレクターの松村慶子である。
その時、まだ無名だったなかにし礼を抜擢したのは、新鮮なセンスを持った若手を起用することによって、ベテランとの差別化を打ち出したかったからだ。
越路と岸は、シャンソン界の大御所だった永田文夫の訳詩による、女性を主語にした歌詞を使っていた。
一方、なかにし礼は、菅原洋一に合わせて男性が主人公の歌詞を書いた。
3人の歌手の競作は、前の年に「夜明けのうた」がヒットしてレコード大賞・歌唱賞に選ばれた岸が圧勝し、ベテランの越路が破れる結果となった。10月に発売された菅原の「恋心」は話題になったものの、売上面においてはまったく刃が立たず圏外に終わった。
ところでこの時、菅原洋一とスタッフたちが秘かに期待を寄せていたのは、カントリーをカヴァーしたB面曲の「知りたくないの」だった。しかし、「知りたくないの」も、期待したほどの好反応を得ることができなかった。
ラストチャンスをものにできなかったことで、菅原洋一が近い内にレコード会社から切られるだろうと心配したなかにし礼は、自分の訳詞が拙かったからだと敗北感にひたっていた。
9月2日に27歳の誕生日を迎えたなかにし礼が、急に心臓発作に見舞われたのは11月半ばのことだ。
真夜中、私は息苦しさに目を覚ました。「空気が足りない」と私は思った。心臓のあたりに針で刺すような痛みが来た。喉の下、左の脇腹、左の背中に今まで感じたことのない痛みがある。激痛でもない。鈍痛でもない。無性に悲しくなるような、この世の終わりのような暗い痛みなのだ。息苦しい。
家の近くにあった救急病院に妻が電話をすると、医者が駆けつけてくれて「心臓発作ですね」と診断した。すぐにニトログリセリンを舐めさせられて、腕に注射されると痛みが嘘のように去っていった。
混乱が落ち着いたところで、医者からは「すぐ入院しましょう。明日からでも」と言われた。その言葉に戸惑ったなかにし礼は、「入院? 心臓病? 一体どうして」とふたたび頭が混乱してしまった。
小さい頃からマラソンも苦手だったし、決して丈夫な子とは言えなかった。だが、高校時代は柔道部の猛練習にも耐えてきたので、発作を起こすほど心臓が弱いとは思ってもみなかった。すると医者が説明してくれた。
「心臓そのものが強い弱いではないのです。あなたの場合は極度の疲労かストレスが原因で冠動脈が痙攣を起こしたのです。一種の自律神経失調症なのですが、それが狭心症を引き起こしたのです」
なかにし礼は11月15日から45日間、聖愛病院の一人部屋に入院することになった。
もともと苦学生だったなかにし礼は、生活費を稼ぐためもあって、シャンソン喫茶で歌っている歌手のために日本語の訳詩を書いてきた。また、文筆業で身を立てようと、内外タイムズという新聞に音楽評を書き、週刊実話という雑誌にはかなりきわどい小説を連載した。
だが、売れっ子の放送作家だった青島幸男に弟子入りして門下生になり、「ポップス専科」というラジオ番組を担当した頃に、放送作家という仕事が肌に合わないことがわかったという。
「ねえ、青島さん、俺やっぱり歌を書こうと思うんですけど」
私は青島さんに、番組収録中、後楽園ホールの客席で相談した。
「ああ、お前はそれがいいよ。お前にはね、歌という逃げ道があるから、放送作家に身が入らないんだよ。シャンソンに戻るのかい?」
「いえ、もう今度は流行歌を書いてやろうと思うんですけど」
「その方がいいよ。人の足もと見て、ズドンと流行り歌書いてみなよ」
歌については、2年前にも偶然に出会った石原裕次郎から、初対面だったのにこんな言葉をもらっていた。
「よしな、よしな! シャンソンの訳詞なんぞどうだっていいじゃないか。あんなもの日本語にしたってつまんねえよ。なんで、日本の歌を書かないのよ。俺が歌っているような。ガツーン!とヒットする歌をよ」(なかにし礼著「黄昏に歌え」朝日新聞社)
ストレスの原因となっていたのは、学生結婚した妻との間で明らかになっていた生き方をめぐる確執であった。妻は純粋な芸術家や文学者であってほしいと願うあまり、シャンソンの訳詩や流行歌の作詞をすることには懐疑的だった。否、はっきり反対で、それを仕事にすることを認めてくれなかったのだ。
なかにし礼は病室に妻が見舞いに来るたびに、「俺が歌を書くの、そんなにイヤかい?」と同じ質問をした。「歌を書くたびに、あなたが不純になっていくような気がするの」と妻は答える。
「ひょっとしたら、俺は歌を書くために生まれてきたのかもしれないぜ」
「それは詭弁よ。あなたにはもっと大きな夢があるはずよ」
「いや違う。先のことはわからない。が、今は、歌が書きたい。何か書けそうな気がする。思い切って書かしてくれ」
「賛成しないわ」
「軽蔑するかい?」
「軽蔑するわ」
私の胸は、発作の予兆のようにチクリと痛んだ。
1966年4月19日、夫婦の間には長女が誕生したが、なかにし礼は別居して作詞家の道を歩み始めていく。そして、1年以上も前に作詞作曲したまま埋もれていた楽曲が松村慶子に発見されたことによって、作詞家としての処女作「涙と雨にぬれて」が日の目を見たのである。
裕圭子とロス・インディオスによってレコード化された「涙と雨にぬれて」は、まもなくビクターが田代美代子とマヒナ・スターズの歌唱でカヴァーした。それはシャンソン喫茶の「銀巴里」でなかにし礼と親しかった田代が、作詞家としての新たな出発を意気に感じて、自分から歌いたいと願ったからだった。
こうして「涙と雨にぬれて」が記念すべき最初のヒット曲になった頃、遅ればせながら菅原洋一の「知りたくないの」にも火がついて、発売から2年後の1967年になって大ヒットを記録する。
ここからあっという間に歌謡曲の作詞家として才能を開花させたなかにし礼は、短期間に数多くのヒット曲を手がけた後、小説や随筆の執筆へと、表現活動の領域を広げて活躍していく。

「なかにし礼と75人の名歌手たち」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから