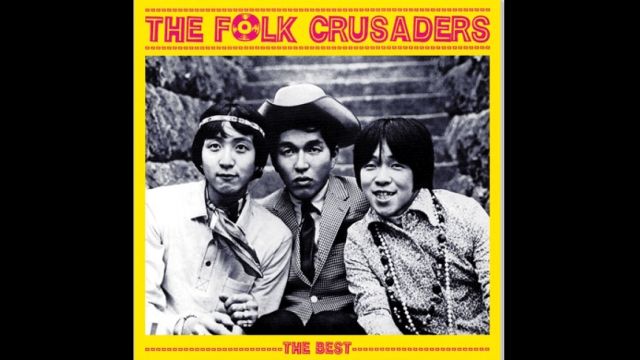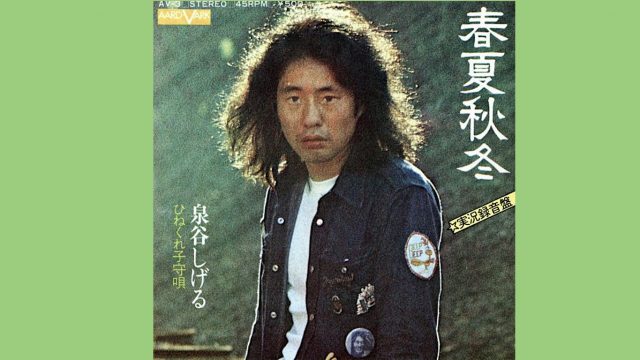ザ・フォーク・クルセダーズ解散後に単身で渡米した加藤和彦は、まずサンフランシスコに行って60年代末のフラワームーブメントを実体験することにした。そこでヒッピーカルチャーの洗礼を浴びて、「あの素晴らしい愛をもう一度」という曲を北山修とのコンビで作った。これはフォークル時代の「悲しくてやりきれない」とともに、単なるヒット曲には終わらず、後世にまで歌い継がれるスタンダード・ソングになっていった。
70年代初頭にヨーロッパへ旅立った加藤はパリからロンドンへと足をのばしたときに、グラム・ロックの抬頭に遭遇している。そうした海外への旅で身につけた音楽的な教養、ヨーロッパのハイ・ソサエティの文化や伝統に触れた体験が、後のプロデュースの仕事に役立ったという。
1960年代なかばから始まったエレキブームやGSブームまでのレコーディングでは、おおむねアレンジャーが事前に譜面を仕上げておいて、スタジオ・ミュージシャンにパートごとの譜面を渡し、演奏を録音するという方法がとられていた。ところが加藤は必要となるであろうと想定したメンバーたち、若手ミュージシャンをスタジオに集めて、アレンジを含むスタジオ・ワークを一緒になって行った。
1973年にヒットした吉田拓郎の「結婚しようよ」でも、事前に準備したアレンジ譜面を使わず、バンドでサウンドを徐々に組み立てながら仕上げた。ボトルネックギターをフィーチャーしたアコースティック・サウンドには、後に松任谷由実のアレンジとプロデュースで活躍する松任谷正隆が弾くバンジョーやハーモニウムが使われた。全編を通して軽やかさを刻んでいるパーカッションは、加藤がイスを叩いて鳴らしたものだった。
このレコーディングを体験した吉田拓郎は、「目からウロコでした。パッ、と目の前の音楽観が広がった」と語っている。この曲のヒットによって新しい女性ファンが急増し、吉田拓郎は時代のアイコンになっていったが、同時に作曲家としても成長を遂げる。それは加藤との出会いなくしては、ありえなかったであろう。
加藤はその後、自分でもサディスティック・ミカ・バンドを結成し、日本人の作るロックを追求してロキシー・ミュージックとのイギリス・ツアーで注目されるなど、積極的に世界へと進出していった。だが残念ながら途中で、バンドが空中分解して帰国、そのことで深い挫折を味わった。

やがて作詞家の安井かずみと結婚して公私ともにパートナーを組むようになって、80年代初頭に”ヨーロッパ三部作”と呼ばれるアルバムをバハマ諸島のナッソー、ドイツのベルリン、フランスのパリで制作している。そのレコーディングに参加していたのが坂本龍一や細野晴臣で、彼らはまもなくYMOを結成することになる。テクノサウンドで世界に認められるYMOも、少なからず加藤からは影響を受けていた。
50歳になった加藤は日本の伝統文化を継承しつつも現代にアピールする、スーパー歌舞伎の音楽にも取り組んでいる。そうした音楽家としての軌跡をみていくと、日本で最初のインデペンデント・プロデューサーだったといわれる加藤が、実は「上を向いて歩こう」で世界に名を残したプロデューサー、中村八大にとって後継者にあたる存在だったのではないかとの思いがしてくる。
彼の弾くアコースティック・ギターは、テクニックも表情も豊かだったと共演したミュージシャンは口をそろえる。作曲家で編曲家、ソングライター、優れた現役のプレーヤーだったというところまで、加藤和彦と中村八大は共通している。そしていつでも「世界」に目を向けていたコスモポリタン、自由人だったところもまた合い通じていたように思う。
そんなかけがえのない人物であったからこそ、彼のつくった音楽とともに語り継いで行きたい。(佐藤剛)