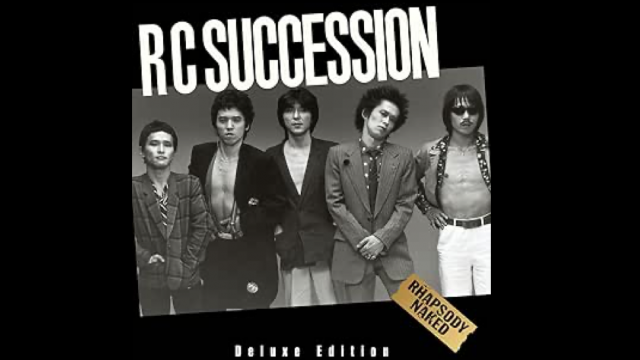1969年にアンドレ・カンドレという芸名で登場した井上陽水のデビュー曲「カンドレ・マンドレ」のアレンジをしたのは、フォーク・グループの六文銭を率いていた小室等だった。
小室はレコーディングが終わってから、まだ地元の福岡から出てきたばかりだった陽水を、どういうわけか自宅に招いた。緊張して上がってしまった陽水は、用意された鍋をほとんど食べれなかったらしい。
だが、それをきっかけにして小室の家に遊びに行くようになった。親切で面倒見がいい小室に、陽水は「終生、頭が上がらない」と感じたという。
ビートルズに出会って以来、一途にその音楽にだけ深く傾倒していた陽水は、小室が持っていた多くのレコードを聴いて、音楽の幅をひろげていった。
中でも特に大きな影響を受けたのが、ボブ・ディランだった。
2015年5月、陽水はトーク番組「小室等の新音楽夜話」にゲスト出演した際に、ボブ・ディランの「ジャスト・ライク・ア・ウーマン(Just Like A Woman)」をものまね風に口ずさみ、途中からは小室もギターと歌で加わった。
二人の会話の中で小室が、影響を受けたという割には、「ディランの楽曲が陽水サウンドに反映されてないような気がするが、あえて?」とたずねるシーンがあった。
「あえて、というか」と保留しつつ、陽水は歌詞について「少し影響を受けたせいで、歌詞がわからないという謗りを受けることになったんですよね」と答えた。
初期の頃から陽水のソング・ライティングは、”うたいながら声でメロディを探していく”というものだった。だからメロディが決まって、そこに歌詞を載せていくのが基本になっていた。
しかし小室の家で歌詞カードを見ながらディランのレコードを聴いていた陽水は、「ジャスト・ライク・ア・ウーマン」で突然、どんなふうに詞を書けばいいのかがわかったのだ。
「Nobody feels any pain(誰も痛みを感じない)」という一行から始まるその歌は、ソングライティングにおける画期的な発見となった。
誰も痛みを感じない
今夜、俺は雨の中を立ち尽くしているというのに
誰もが知っているのは
彼女が新しい服を手に入れたってことだ
でも最近ではリボンや飾りが
カールした髪から落ちたみたいだ
彼女は女の如く奪い、そうさ
彼女は女の如く愛を交わし
そして彼女は女の如く痛みを感じる
だが、少女のようにわっと泣き出すのだ
最初の六行は何を言ってもいいから、最後の四行でビシッと言いたいことを決める。それが最大の発見だった。のちに陽水がこんなふうに語った文章が残っている。
「”She takes just like a woman”に至るまでの最初の六行というのは、何をいってもいいんだということなんだよ。とにかくそこまでの一行一行は、何かインパクトのある”Nobody feels any pain”とか何とかわけの分からないことをいっておけばよくて、むしろそこまで意味のないことをいっておけばおくほど最後の四行が生きる」
そしてもうひとつ、もっと大事なことにも陽水は気づいていた。ディランはじつに見事に、韻を踏んだ詩を書いていたのである。
そのことから意味よりも言葉の韻を優先させるほうが、聴き手の想像力をはるかにかきたてることがわかった。ストーリーに忠実な歌詞だと聴き手の想像の域を出ないが、韻を優先させると想像の域を出てしまうことがある。だから思わぬ面白みが生まれてくるのだ。
そんな発見から生まれた歌が、生涯の代表作となる「氷の世界」だった。
「”Just like a Woman”という一番大事なところが、おれの歌では”毎日、吹雪、吹雪、氷の世界”というところなわけよ。その言葉がありさえすれば、あとはもう窓の外でリンゴを売ろうがキュウリを売ろうが何でもいんだと思ってたよ」
井上陽水オフィシャルサイトはこちらから

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから
※井上陽水の発言はいずれも、海老沢泰久著「満月 空に満月」(文芸春秋)からの引用です。
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから