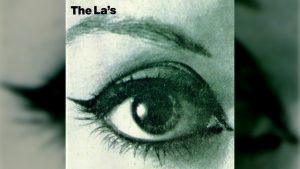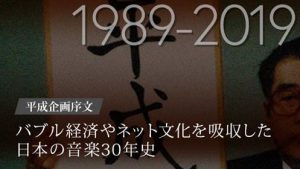平成9年、西暦でいうところの1997年。シングル曲の売り上げがピークに達し、のちに「CDバブル」と呼ばれるようになった年に、中村一義の1stシングル「犬と猫」はリリースされた。
♪ どう?
町を背に僕は行く。今じゃワイワイ出来ないんだ。
奴落とす、もう。さぁ行こう!
探そぜ、奴等…ねぇ。
もうだって、狭いもんなぁ。
「どう?」や「ねぇ」といった、それまでの日本語のポップスよりもさらにくだけた口語体を、独特の感性でメロディに乗せていく。
それはまるで英語の歌を聴いているようでもあり、「んで」と歌えば「and」のように響く。一聴しただけで全ての歌詞を正確に聴き取るのは非常に困難だが、歌詞を見ればハッキリと聴き取れる。
そんな誰も聴いたことがなかった、それでいてとてもポップなサウンドは、まさに新しい時代の到来と呼ぶにふさわしい音楽だった。
そうした歌い方について、中村一義は自伝本「魂の本 ~中村全録~」でこのように話している。
昔のテレビ番組で甲本ヒロトさんが「俺たちはサザンオールスターズの次の世代だから歌詞をハッキリ歌うんだ」って言ったんですよ。それを観て「だったら俺はブルーハーツの次の世代だから、ハッキリ歌ってるんだけど歌詞がわからない歌を歌おう」と思ったんですね。
中村一義がはじめてブルーハーツを聴いたのは小学生のときだ。深夜のテレビから流れてきた「パンク・ロック」を聴いて、聴き手に向けた個人的でまっすぐな叫びに、心を打たれたのだという。
♪ 僕 パンク・ロックが好きだ
中途ハンパな気持ちじゃなくて
本当に心から好きなんだ
高校卒業とともに本格的に音楽制作をはじめた中村一義は、そんなブルーハーツにいつか恩を返したいと感じていた。しかし、はじめから日本語で歌詞を書いていたわけではなく、その頃はすべて英語で歌詞を書いていたという。だが、レコード会社にデモテープを送っても、色よい返事が返ってくることはなかった。そして時折「日本語の歌詞にトライしてみたら?」というコメントがあるだけだった。
そんなある日、地元の商店街を自転車で走っているときだった。ふと、ボブ・ディランの「ライク・ア・ローリング・ストーン」のサビで歌われる「ハウ・ダズ・イット・フィール?」をどう訳すか考えたという。
それで「ハウ……ハウ……どう……どう? どーう!」って。そこから「ホッパーとポッパー」、後の「犬と猫」が生まれたんです。だから「どう?」が、すべての始まりだったんですよね。
「どう?」という言葉は、何のために生きているのか、というアイデンティティへの問いかけだ。幼少時代は家にも学校にも居場所がなかったという中村一義にとって、それはとても重い言葉であり、難題だった。
「お前はどうなんだ?」「そこに対する答えを持っているのか?」って、そのことを考える十何年間だったんだなあ、と思って。それを、たった二文字とハテナだけの「どう?」で表現できたときは、本当に嬉しかったですよ。
くだけた口語体とポップなサウンドの奥にあるのは、十何年間を生きてきた人間の重み、ブルーハーツから受け継いだ初期衝動的な叫びだ。そしてその叫びは、同じ時代を生きる若者たちから多くの共感を得るのだった。
♪ どう?
僕として僕は行く。僕等、問題ないんだろうな。
奴は言う、こう…。「あぁ…ていのう」。
もう、けっこう!
引用元:『魂の本 ~中村全録~』中村一義・著(太田出版)

「金字塔」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから
TAP the POP協力・スペシャルイベントのご案内
【オトナの歌謡曲ソングブックコンサート in YOKOHAMA】開催

1917年に開館した横浜の歴史的建造物「横浜市開港記念会館」(ジャックの塔)で、昭和の名曲を愛する一流のアーティストが集ってコンサートを開催!
昭和に憧れる若い人からリアルタイムで昭和歌謡に慣れ親しんだ人まで、幅広い世代が一緒に楽しめるコンサートです! “国の重要文化財”という、いつもと違う空間が醸し出す特別なひとときを、感動と共にお過ごしください!!
▼日時/2025年6月7日(土曜) 開場17時/開演18時
▼場所/横浜市開港記念会館講堂(ジャックの塔)
▼出演
浜田真理子 with Marino(サックス)
畠山美由紀 with 高木大丈夫(ギター)
奇妙礼太郎 with 近藤康平(ライブペインティング)
タブレット純(司会と歌)
佐藤利明(司会と構成)
▼「チケットぴあ」にて4月5日(土曜)午前10時より販売開始 *先着順・なくなり次第終了
SS席 9,500円 (1・2階最前列)
S席 8,000円
A席 6,500円
「チケットぴあ」販売ページはこちらから
▼詳しい情報は公式サイトで
「オトナの歌謡曲ソングブックコンサート in YOKOHAMA」公式ページ