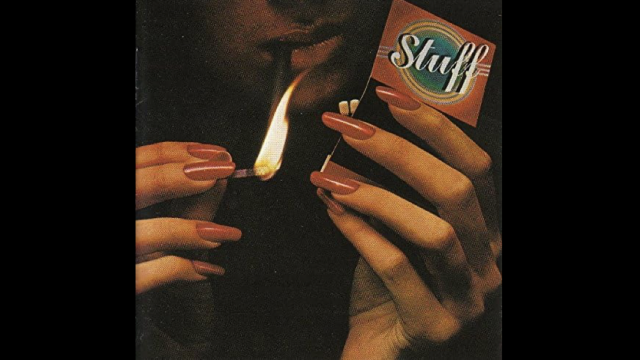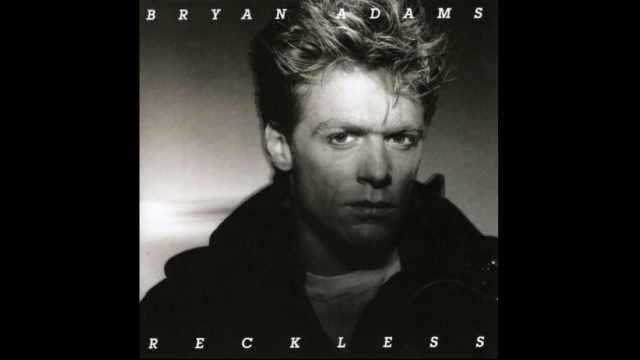サンフランシスコは激しい雨だった。
その日の稼ぎを確保するためには、もうひとりかふたり、客が必要だった。
運よく、前方で手を上げている女性が見えた。
彼が信号で停まると、彼女はタクシーに乗り込んできた。
「どちらまで」と、彼はブルーのガウンを纏ったその客に声をかけた。
「この雨では、その素敵なガウンも台無しですね」
彼女は窓の外を見たまま、目的の住所を告げた。
彼女は窓の外を見続けていたが、その懐かしい顔を彼が思い出さないわけがなかった。
「失礼ですが、どこかでお会いしたような。。。」と彼は言った。
「人違いですわ」と彼女は言ったきり、口を閉ざした。
だが彼は、鏡の中に、彼の運転ライセンスの名前をチェックする彼女の姿をとらえていた。
彼女の表情が少しずつ笑顔に変わり、そしてすぐ、悲しげなものとなった。
「元気だった、ハリー?」と彼女は言った。
「君は、スー?」と彼は言った。
あの頃も、彼はよく車で彼女を家まで送ったものだった。
愛の意味を知ったのも、ドッジの後部座席だった。
あの懐かしい日々がつい昨日のことのように、彼には思えた。
女優になるの。それが彼女の夢だった。
パイロットになって大空を飛ぶのさ。それが彼の夢だった。
彼女は演劇の世界に進み、彼はパイロットになるための学校に進んだ。
それから。
視力の問題もあり、彼はパイロットの道を断念していた。
そして飛行機ではなく、タクシーのハンドルを握っている。
だが、夢を捨てたわけではなかった。
3ヶ月タクシー・ドライバーとして働くと1ヶ月休暇を取る。
その休みの間に演劇の脚本を書き、主題歌を作る。彼はそんな生活を過ごしていた。
何本か小さな劇場で上演された作品もあった。彼女を想って書きためた歌もあった。
彼女は…窓の外を眺めていた。
彼女の瞳に何が映っているのか、彼女があれからどんな人生を送って来たのか、彼にはわからなかった。
そしてあっという間に、時が流れ、タクシーは彼女の告げた目的地に到着した。
「ありがとう。また違う場所で会えるかしら」と彼女は言った。
「お釣りは取っておいて…」
雨の中、彼女が車を降り、歩き去っていく様子を見守り、
彼はひとつの物語が終わったように感じながら、車のアクセルをゆっくりと踏み込んだ。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから