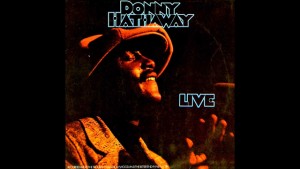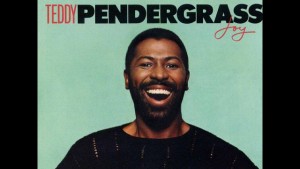〈はじめに〉
ぼくがパプアニューギニアに出発する少し前に、中国では天安門事件が起こった。
日本のマスメディアはその3年前、1986年から始まったバブル景気を煽り続けていた。
就職は売り手市場だったし、ディスコなどでバカ騒ぎをする若者もいた。
当然ながら、こんなに実際の価値を超えて額面だけ地価や株価が高騰し続けるのは、あまりにも不自然で長続きするはずがないという意見も一部にはあった。
天安門事件で世界の不安定さを感じた人もいた。
しかし実際にバブルが崩壊して企業の倒産や人員整理が相次いだのは、平成3年からのことでまだ先の話だった。
平成元年、世間はバブルを謳歌していたのだ。
とはいえ、バブル崩壊とは別の意味で社会の崩壊は進んでいた。
1970年代半ばから2005年まで、多少の変動はありながらも日本の出生率は下がり続けた。
平成元年はその低下の真っ只中にあった。
2019年4月28日 中澤 港
どちらが原因でどちらが結果かはわからないが、出生率の低下と子供の価値には密接に関係してくる。
子供一人当たりにかける育児コストは、出生率とは逆の変化を示すのが普通だし、兄弟姉妹や近所の同年代の子供が少ないと、無意識のコミュニケーションを体得するのは難しくなると言われている。
核家族が普通になっていたことと相俟って、平成に入ると人と人のつながりは希薄になっていった。
最近流行の言葉でいえば、ソーシャル・キャピタルが低下していったのだ。
出生率の低下とともに、所得格差の拡大も始まっていた。
先進国の多くで所得格差の拡大と財産の相続による社会階層の固定化が進行していった。
低所得階層の若者が感じる閉塞感は、ますます強くなっていく一方になった。
社会が分断化され、人を信じることが難しくなっていく。
1988年にブルーハーツが出した「TRAIN-TRAIN」は、平成とほぼ同じに始まった学園ドラマ『はいすくーる落書』(主演:斉藤由貴)という、不良生徒の比率が高い工業高校を舞台にしたドラマの主題歌になった。

「♪ 栄光に向かって走る あの列車に乗っていこう」と始まる歌詞には、「見えない自由が欲しくて 見えない銃を撃ちまくる 本当の声を聴かせておくれよ」と、社会の壁に対峙して苦悩する若者への共感が示されている。
サビでは「♪ TRAIN TRAIN 走ってゆく TRAIN TRAIN どこまでも」と、そういう若者を応援する気持ちがよりストレートに出ていた。
当時のブルーハーツの曲はメッセージ性が強く、「チェルノブイリ」とか「首切り台から」などでは、アナーキーに社会を批判していた気がする。
もっとも平成になる前、昭和の終わりに人気があった尾崎豊や横浜銀蠅など、社会化できない若者が大人社会との軋轢を歌にするというスタイルのロックは、いつの時代にも巷に溢れていた。
ブルーハーツは若干、毛色が違うような気はするが、個人の視点で社会を批判するというスタンスは共通していたと思う。
そういう意味では昭和の終わりまでの日本のロックは、1960年代から70年代に若者に支持された岡林信康や吉田拓郎、井上陽水などフォークの流れを継いでいたのではないだろうか。
若者の成長には社会化する側面と内面的成長の2種類があって、昭和の時代に人気があった学園ドラマは、教師が若者の苦悩に共感を示しつつも、社会に若者を適応させる役割を担うものがほとんどだった。
その最たるものが、武田鉄矢主演の『三年B組金八先生』シリーズだろう。
ただし、第2シリーズのクライマックスで、中島みゆきの「世情」が流れる中、不良とされる生徒たちが人間として大事なものを守ったが故に、学校に踏み込んだ警察官に捕まって補導されていくシーンは、社会への適応よりも大事なことがあるかもしれないというメッセージを発していたが…。

中村雅俊や山下真司、あるいはもう少し時代が下がると『ごくせん』(主演:仲間由紀恵)など、教師がレールを外れた子供に理解を示しつつも、如才なく社会の一員に引き戻すという物語が基本になる。
それらは現在の社会を変えなくても、存在できる場所を見つけてあげる、という話の枠内に収まっていた。
教育とは野生の子供を社会化させることであると、それを意識的にやったのが『女王の教室』(主演:天海祐希)だった。
一方、社会は絶対じゃないし善悪の判断も状況によって変わるから、もしかしたら状況の方が間違っているのではないかというスタンスで、内面的成長を刺激した作品は1994年(平成6年)に放映された『アリよさらば』(主演:矢沢永吉)の辺りから始まっている。
これはドラマ名と同じ主題歌の歌唱も印象的だった。
平成11年に出版された高見広春の小説「バトル・ロワイアル」(太田出版)に描かれるのは、成功したファシスト国家の犠牲としてもたらされた極限状況の中で、中学生の子供たちが内面的に成長する姿であった。
ファシスト国家の走狗として嬉々として生徒を国家への人身御供とする教師の名前が坂持金発であり、明記はされていないが金八先生=坂本金八をモデルにしていた皮肉を効かせてていた。
物語の中で最も成長する主人公である七原秋也が、ボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンを愛するロック少年で、「We are born to run」という心の叫びとともにエンディングを迎える。
そこには、ロックには世界を変える力があるという主張が溢れていた。
我が身かわいさから、恐怖心から、あるいはサイコパスだったり、虐待を受けていた経験から、生き残りゲームに乗ってクラスメイトを罠にはめたり躊躇無く殺したりする生徒もいる中で、七原秋也は友を信じることをやめず、連帯を強めながら、総統によって支配された社会から捨てられた、クラスの全員が生き残る道を探そうとする。
その姿は、もしかしたら、2016年(平成28年)から少年ジャンプで連載されている漫画「約束のネバーランド」でのエマの描かれ方に影響を与えているかもしれない。
共感と信頼と連帯は、社会の分断に抵抗する唯一の方法である。
しかし平成の日本ではそうした意味でのロックは廃れ、体制迎合的なポップスばかりがメジャーシーンに溢れるようになった。体制と反体制、あるいは体制に適合できずドロップアウトする人々との分断が進行した。
「勝ち組」が存在するということは、「負け組」が裏にいるという不幸な状態が前提となる。
それなのに、その現実からは目をそらして、「勝ち組」になりたがる人ばかりが増えていった。
分断が生まれる原因の一つは、世の中に溢れる情報がヒトの合理的な情報処理の容量を超えてしまったことにある。
そのために直感や先入観に基づいて注目すべき情報を限定し、過去に上手くいった行動パターンを選択する人が多くなった。
この傾向は認知バイアスと呼ばれる。
平成の30年間を通じたインターネット、とくにソーシャルメディアの発達によって起こった情報量の爆発的増大が、この傾向を加速したことは間違いない。
悪くはないけれども、なぜこれが爆発的に売れるのかわからないような曲が大ヒットしたのも、平成の音楽の特徴だろう。
しかもヒット曲はそれ1曲だけ、というようなミュージシャンも多かったような印象がある。
そこにはランキングやチャートによって生み出される認知バイアスが、「みんながいいんだからいい」という購買動機となっていくという、ヒット曲生成のメカニズムにも関わってくる問題があった。
したがって単にヒット曲を追う方法では、平成という時代の音楽やJ-popを通覧することにならない気がする。