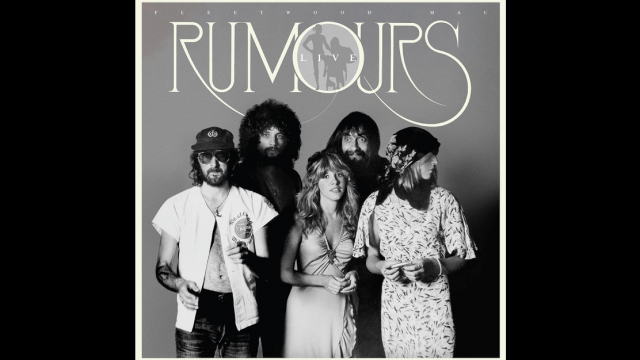人気作詞家になってヒット曲を量産し始めた阿久悠が、音楽業界に次なるイノベーションを巻き起こしたのは、旬を過ぎたアイドル歌手の山本リンダに書いた「恋のカーニバル」によってだった。
大人の歌手への脱皮を狙って作られたその歌は、若くてスタイルがよい女性がセクシーな衣装や振り付けで、テレビの画面からアピールして歌うことを前提にしていた。
そもそもの企画は学習院大学を卒業して間もない若手の作曲家、都倉俊一のところに作曲の依頼があったところから始まった。
次々にヒット曲を作り出していた都倉は歌手の名前を聞いて、「ああ、あの舌ったらずの歌手」というもので、あまり食指を動かされなかった。だから所属していた事務所に「断ってください」と頼んでおいたという。
数日たって、リンダの件でどうしても会いたいという人が来ているということで、当時フジテレビのプロデューサーであった吉田斉という人に会った。あまり乗り気ではない私の様子に多少気を使いながら、彼は自分の考えを話し始めた。
「私はテレビが専門で音楽はわからないが、テレビ的に見るとあのリンダという子は面白いと思う。何とか協力してくれないだろうか」という話であった。話をしていくうちにテレビという映像と音楽の組み合わせにより、何かできるかもしれないという気になってきた。
映像を思い浮かべながら作曲をするというのはあまりやったことのない手法だったが、都倉はほとんどの場合、作曲と編曲を同時にやっていた。だからまず、どういうイントロから始めようかと考えてみた。
セクシーな美女がイントロでどんな登場の仕方をしたらインパクトがあるのか、そうしたことを思い浮かべて、リズムは南米のサンバにすることに決めた。
そしてこの仕事を正式に受けることにして、作詞は勢いのある阿久悠に依頼することにした。
それまでは作詞家から詞をもらって、それに曲をつけるのが普通だった。だが、このときは作曲と編曲を先に進めてカラオケまでレコーディングし、それにメロディーを入れて阿久悠に渡した。
その手法はその後、山本リンダのプロジェクトだけでなく、阿久悠とのソング・ライティングでは常套手段になっていく。単なるソングライティングではなく、プロデューサー的な立ち位置である。
そして阿久悠から「恋のカーニバル」といいうタイトルの歌詞が出来上がってきた。
そこから起こった一番の問題は、山本リンダの舌ったらずな歌い方だと、言葉がリズムに乗らないことだった。強力なサンバのリズムに速いテンポの日本語なので、それまでの歌い方では歌いこなせない。相当な時間のレッスンをしても上達せず、一向に進歩がないまま行き詰った。
一方では大胆なへそ出しルックの衣装や、南米のサンバのリズムにのせて生命力に満ちたダイナミックな踊りが決まって来た。都倉はそこで、極端に母音を強調して歌わせてみた。
“うわさをしんじちゃいけないよ”ではなく、“うぅ、わぁ、さぁ、をぅ、しぃ、ん、じぃ、ちゃぁ”である。
つまり日本語を英語風に発音させたのである。とたんにノリがよくなった。彼女もそれを感じたらしく、歌全体が生き生きとしてきた。
レコーディングが終わると、誰からともなくもっとインパクトのあるタイトルで行こうということになった。現場で雰囲気を共有していた阿久悠も、そのときのことを著書『歌謡曲の時代 歌もよう人もよう』(新潮社 2004年)で、こう述懐している。
レコーディングを終わって考えが変わった。出来上がった楽曲の面白さ、歌唱のユニークに比べて、いかにもタイトルが平凡に思え、詞の最後の行の部分の言葉をそのままタイトルに使った。これが運命を変えた。
山本リンダのカムバックに関わっていた関係者たちは当然、大人の男性をターゲットに想定してプロモーションを行った。
ところが実際にレコードが発売になると、レコード店の前に行列を作っていたのは子供たちだった。お母さんに連れられた、就学前の小さな女の子たちもいた。
激しいリズムに乗ってテレビに登場した山本リンダに、子どもたちは言葉や理屈ではなく視覚と身体で反応したのだ。そしてアクションを真似てそれをすぐに覚えてしまった。
へそ出しルックで踊りながら歌う山本リンダは子どもたちにとって、架空の物語の主人公か妖精のようなものだったのかもしれない。当初に意図していたターゲットの若い男性だけでなく、それとまったく異なる子どもたちにも支持された。
ここから日本の社会で、全く新しい音楽の受容が始まったといえる。そのことで「どうにもとまらない」は歌謡曲を楽しむ層を、幼稚園児から小中学生にまで拡張した。これは後年に巻き起こった、ピンク・レディー現象のさきがけである。
そして”時代”をとらえるアンテナを持つ阿久悠や都倉俊一が、ヒット曲を生み出すソングライターに留まらず、”時代”を動かすプロデューサーとなっていった。
(注) 都倉俊一さんの発言は、都倉俊一著「あの時、マイソングユアソング」(新潮社)からの引用です。

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから