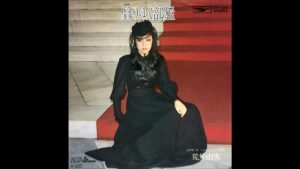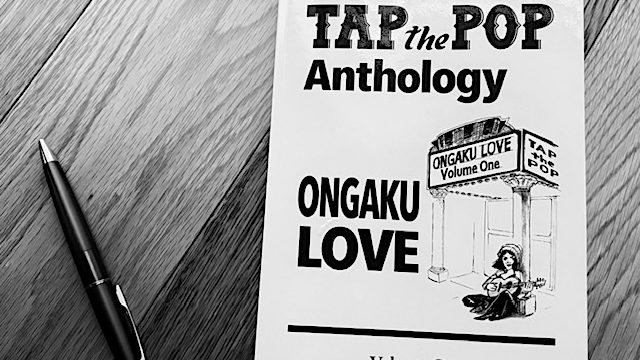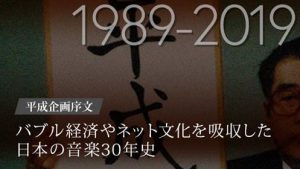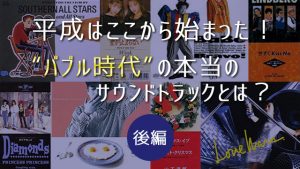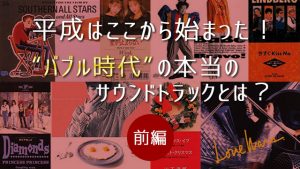昭和元年と昭和64年は、ともに7日間しかなかった。したがって昭和という時代は、昭和2年から昭和63年まで、西暦にすれば1927年から1988年までの約62年間であった。
それを半分に割ると、前半が1927年から1957年まで、後半が1958年から1988年までの31年間となる。
それぞれの31年をポピュラー・ミュージック(大衆音楽)という視点から見ていくと、戦前から戦後復興にかけての前半の昭和は、「流行歌」の時代といえる。
そして、高度成長期からバブルが弾けるまでの後半の昭和は、ロックやフォークの影響を受けるなかで、「歌謡曲」が全盛を迎える時代となった。
偶然なのか、必然なのか、1989年に始まった平成も、2019年4月末日までなので31年間となる。
平成に入ると、「歌謡曲」の中のポップスが、「J-POP」に受け継がれて呼称も代わり、コンピューターを使った音楽作りの比重が増えていった。
レコードやテープからCD、インターネットでのダウンロード、ストリーミングと、音楽を伝達するメディアも大きく変化しながら現在に至っている。
平成を象徴する音楽家になる椎名林檎が、シングル「幸福論」で音楽シーンに登場してきたのは、平成という時代が10年目を迎えた1998年のことだった。
椎名林檎の革新性は何よりもまず、斬新かつ大胆な楽曲を作るソングライターだというところにある。
しかも、それを自ら歌で表現できるシンガーであり、アレンジや打ち込みもできるミュージシャンであり、自分を客観視してプロデュースできるアーティストでもあった。
「幸福論」は、歌の歌詞という常識をくつがえす散文スタイルで、ポップスでは滅多に使われない「哲学」などという単語も出てくる。
そして翌1999年2月に、デビュー・アルバム『無罪モラトリアム』がリリースされると、本格的にブレイクしてベストセラーとなり、新しい表現者として世に受け入れられていく。

『無罪モラトリアム』
前半の昭和にあった「流行歌」の時代に、女性のソングライターはほぼ皆無だった。後半の昭和である「歌謡曲」の時代になってようやく、岩谷時子や安井かずみといった女性の作詞家が活躍し始めて、道が拓けていった。
それに続いたのが加藤登紀子、荒井(松任谷)由実、中島みゆきといった、女性のシンガー・ソングライターたちであった。
彼女たちは成長していくにつれて、プロデュースの領域にまで進出し、「アーティスト」と呼ばれるようになった。いずれも自分の作品を書いて歌うだけではなく、他者に作品を提供することで、ソングライターとしても実績を上げている。
そうした先駆者たちの歩みの延長線上に、忽然と現れたのが、19歳の椎名林檎である。
それまでの日本の歌の概念には収まらない大胆な楽曲を作り、自らの音楽でそれらを表現するという意味で、彼女は最初から「アーティスト」だった。
なお、その年の9月22日に発売されたオムニバス『Dear Yuming〜荒井由実/松任谷由実カバー・コレクション〜』で、椎名林檎は荒井由実の「翳りゆく部屋」をカヴァーしている。
そんな椎名林檎が活躍するのと時を同じくして、15歳のシンガー・ソングライターである宇多田ヒカルがデビューし、ファースト・アルバム『First Love』が空前の売上を記録する。
日本の音楽シーンは1998年から99年にかけて、年若い2人の女性が才能を開花させたことで、新たな時代へと突入していったのだ。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから
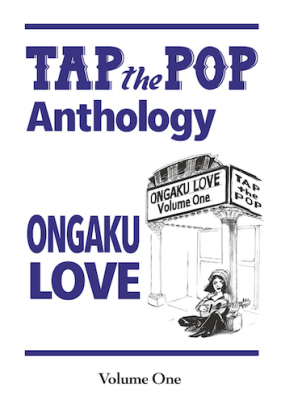
- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから