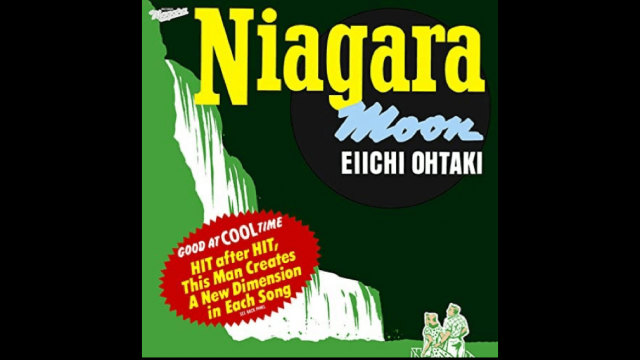大瀧詠一は長い間、自分がミュージシャンになったのは、「エルヴィス・プレスリーに憧れて、ロック・ミュージックに興味を持ったから」だと思い込んでいたという。
だが、実際にはアメリカのエルヴィスでなく、日本のアキラ、すなわち小林旭のほうが先だったことに、1970年代の後半になってから気づいた。それは、はっぴいえんどを解散した後に、日本の音楽史を改めて研究し始めてから分かったことだった。
1985年(昭和60年)10月12日に開かれた小林旭のコンサート、『芸能生活30周年記念リサイタル「-雑草・人生・男道-」』の記念パンフレットに、大瀧はこんな文章を寄稿した。
数年前エルビスと同じ位、この人にも憧れていたことに気づきました。というのは、小学生当時、皮ジャン姿に白いマフラーをなびかせて歩いていた人を見かけて、強く印象に残っていたことを思い出したからです。
それがエルビスに結びついたのだと堅く信じていましたが、当時その格好をしていた人に憧れていたのは、エルビスではなく、アキラだったのです。
そして再びレコードを聞き直して改めて知ったことは、映画館に響き渡っていたあの「ズンドコ節」「ダンチョネ節」のカン高い声が、私の心に奥深くしみ込んでいたことでした。

大瀧詠一による監修・選曲『アキラ 3』
1985年の秋に、味の素ゼネラルフーヅ「マキシム」のCMソングとして、小林旭の「熱き心に」を企画したのはON・アソシエイツのプロデューサー、大森昭男である。
「サイダー’73」を作って以来、CMの分野で大瀧との関係をずっと築いてきた大森は、サントリー・ウィンターギフトのキャンペーンに、森進一の「冬のリヴィエラ」(作詞/松本隆、作曲/大瀧詠一、編曲/前田憲男)を使って大ヒットを放っていた。
1981年のアルバム『ロング・バケーション』を大ヒットさせた後に、アルバム『EACH TIME』を1984年に発表してナイアガラサウンドを完成させた大瀧は、そこから自然に創作活動を休止した状態にあった。
作曲活動も1年半以上にわたって休止していることを知っていた大森は、それにかまわず大瀧のもとを訪ねると、自信に満ちた笑顔でこう切り出したという。
「大瀧さん、今度は逃げられませんよ」
大森のただならぬ気配を察知して、大瀧は先手を打つかのようにこう切り返してきた。
「この中に入っているようなものだったら断りますよ」
大瀧はそれから、ビール、化粧品という具合に商品やクライアントを5つあげていった。しかし、大森がずっと首を振るばかりだったので、その後に10まで増やしたが状況は変わらなかった。
その時点で「参りました」と大瀧がいうと、おもむろに「小林旭さんです」という一言が大森から出てきた。
返事がないまま、そこで長い沈黙が続いたのは、その言葉を天命と受け取った大瀧が、瞬間的に創作モードに入ってしまったからだ。小林旭の代表作である「さすらい」と「惜別の歌」を思い浮かべて、どちらの線で行こうかと、大瀧はしばらく沈思黙考していたのである。
最後まで悩んだ結果、二つのタイプを作って選ぶことにした大瀧だったが、なんと両方ともうまく出来てしまったという。そこで一つに絞れなくなり、ふたつを「エイ・ヤッ!」とばかりに1曲にまとめることを思いつく。
そのために壮大なスケールの曲が出来上がって、それを作詞家に委ねることになった。当初はふたりとも暗黙の了解として、「冬のリヴィエラ」と同じ松本隆を想定していた。
だが、完成した曲と小林旭のイメージから、大瀧が急きょ、大森に対してスケール感のある詞を書ける阿久悠に頼めないかという変更案を出してきた。「松本の都会調の少し弱々しい感じはアキラさんには合わない」と思ったのである。
初めて大瀧に会って作詞の打ち合わせをした時のことを、阿久悠がこのように記している。
あまり、しゃべらなかった。しかし、クレイジー・キャッツの歌に興味があるとか、小林旭の初期の頃のアンチャン節風のものが好きだとか、ちょっと不思議な人だなと思った。ぼくは、可能な限り美文調をメロディーにあてはめ、日本離れのした風景と、現実離れのした浪漫を書いた。
こうして完成した「熱き心に」だったが、デモテープを受け取った小林旭はどことなく、曲の感じがつかめなかったという。そして気持ちが乗らないまま、レコーディング・スタジオに足を運んだ。
なんとなく気乗りがしなかった曲だが、スタジオでストリングスのイントロを聴いて、それまでの疑問が払拭された。そうか!これは『西部開拓史』なんだと。ハリウッド映画の音楽で、雄大な景色のなか、疾走する駅馬車、馬にまたがる主人公の姿などが、一瞬にして思い浮かんだ。その時に、大滝さんの狙いがわかった。
念願かなって憧れのスターと仕事をした大瀧もまた、スタジオで小林旭の力強い歌声を聴きながら、「これは行けるぞ!」と高揚感に包まれていた。
1985年11月20日にリリースされた「熱き心に」は、年末から翌年にかけて大ヒットし、押しも押されぬ小林旭の代表作になっていったのである。


熱き心に [EPレコード 7inch]
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから