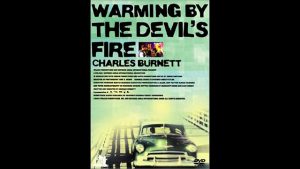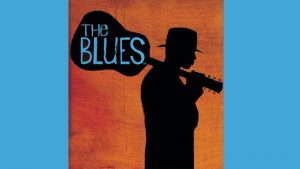『フィール・ライク・ゴーイング・ホーム』(Feel Like Going Home/2003/マーティン・スコセッシ監督)
2003年。アメリカでは「BLUES生誕100年」と称して、CD・書籍・番組・ラジオ・コンサートといったメディアミックスを通じて“魂の音楽”を伝えるプロジェクトが展開された。中でも音楽ドキュメンタリー『THE BLUES』は、総勢7名の映画監督が様々な角度から“魂の音楽”をフィルムに収めて大きな話題を呼んだ。
今回紹介するのは『フィール・ライク・ゴーイング・ホーム』(Feel Like Going Home/マーティン・スコセッシ監督)。ブルーズの源流を求めて、ミシシッピ・デルタから西アフリカのマリまでを旅する物語だ。
冒頭はミシシッピの森のある丘陵地帯。ファイフ奏者の伝説的存在オサー・ターナーがドラム隊を従えて庭を練り歩くシーンから始まる。ファイフとは横笛のことで、竹笛と草笛の中間のような音がする。自作のファイフとドラムによるこのオールド・ニグロ・スピリチュアルは、南部黒人の音楽の中でも最も古いものとして知られている。アフリカ直系の強烈な鼓動を感じすにはいられない。
故・駒沢敏器の著書『ミシシッピは月まで狂っている』には、オサー・ターナーに関するエピソードが記されている。オサーが初めてファイフを目にした日のことだ。
ある日、葦を手にした老人が丘からやって来た。幼い俺はその老人に聞いたんだ。
「おじさん、それは何ですか?」
「これはファイフだよ、ベイビー」
「僕にも作ってくれませんか」
「お前がいい子にしていて、ママの言うことをよく聞けば、作ってやってもいいぜ」
ある日の夕方のことだ。彼の住む場所へ行ってみた。中を覗くと、「あの坊やだな、こっちへ来い」という声が聞こえてきた。俺は恐る恐る中へ入って行った。するともう、ファイフができていたのさ。
「これがお前のファイフだ。どうせすぐには吹けやしないけどな」
「だめかもしれないけど、一生懸命やってみます」
旅の案内人はコーリー・ハリス。1969年生まれの彼は10代の頃にブルーズに目覚めたという世代。コリーは言う。
僕はブルーズに自分の先祖や歴史との結びつきを感じる。どの曲も歴史の一面を語っていて、ブルーズを演奏することで僕は理解した。自分を知るには過去を知るべきだし、行く道を知るには来た道を知るべきだと。
こうして旅はブルーズの故郷ミシシッピから始まっていく。コーリーはロバート・ナイトホークの息子サム・カーやウィリー・キングに会う。ウィリーはブルーズとは「厳しい現実に明日への糧を与えるために生まれた」と言う。「ブルーズはひどい女のことを歌っているが、実はあれは“ひどいボス”のことを意味するんだ。そのまま歌っていたら、木に吊るされて死んでるのがオチだからね」
綿花畑の呻き。黒人たちは早朝から日没まで、賃金を与えられることなく働かされていた。労働や扱いも酷かったが、何より絶望させたのは、目覚めた途端に昨日と同じことを繰り返さなければならないという現実だった。呻きはそんな地獄のような日々から絞り出された。
タジ・マハールやケヴ・モとのセッションを経て、コーリーは遂にオサー・ターナーと対面する。そしてアフリカのリズムが起源であることを感じるため、導かれるようにして西アフリカのマリへと向かう。コーリーがそこへ辿り着くまでには、ジョニー・シャインズやジョン・リー・フッカーなど数々のブルーズ伝説が語られる。
1930年代。サン・ハウスはチャーリー・パットンやウィリー・ブラウンと組んで3人でジューク・ジョイントを回っていた。そんなある土曜の夜のこと。一人の少年が何度も自分を見に来ていることに気づく。少年はギターを弾きたがっていて、両親が寝静まった後、窓からこっそり抜け出して3人の演奏を聴きに来ていたのだ。しかし、少年の弾くギターは酷く、人々は「頭が変になりそうだ」と嘆いた。サン・ハウスは少年に言った。「もうやめるんだ、ロバート。お前にはギターは弾けないよ」
それから1年後の土曜の夜。サン・ハウスらがいつものようにプレイしていると、ギターを背負ったロバートが突然入ってきた。笑っていると、ロバートは彼らの前に立った。
「お前、まだギターを持ってるのか。宝の持ち腐れだろう?」
「じゃあ、教えてやるよ」
「何だと?」
「ちょっと席を代わってくれ」
「いいだろう。口だけじゃないことを祈るぜ」
数分後、サン・ハウスは驚きのあまり言葉を失ってしまった。遂にロバート・ジョンソンが本領を発揮し始めたのだ。
「あの子は俺たちの誰よりも、ブルーズをたっぷりプレイできた」
1941年8月31日の早朝のこと。人類学者のアラン・ロマックスは、ミシシッピのプランテーションの広大な平野を訪れ、そこで労働する黒人たちと接触する機会を得た。使命感の強いアランはレッドベリーの初録音たちも立ち会ったことのある熱心な録音採集家だった。彼が探していた男は自己紹介をした。
「マッキンリー・モーガンフィールド。ニックネームはマディ・ウォーター。ストーヴァル農園の名高いギター弾きだ」
西アフリカのマリに到着したコーリーは、「ここは何もかも懐かしく、新しくもあった」と心の風景を口にする。アメリカからやって来た男を出迎える子供たちはみんな笑顔で溢れている。
サリフ・ケイタは「我々は生まれた瞬間から音楽とともに生きている」と言い、「僕にとってのブルーズは恋や人生なんだ。でもアメリカのブルーズは奴隷制を思ってしまう」と悲しむ。
ハビブ・コイテは「僕らには多種多様な音楽がある。各民族の音楽がアメリカで一つになった」
アリ・ファルカ・トゥーレは「黒人のアメリカ人はいない。いるのは黒人だ。我々は結ばれるべきだ。アメリカの黒人たちはアフリカに来て自分たちを外国人と思わなくていい。ここがルーツなのだから」
コーリーの旅はオサーとのセッションで締めくくられる。それはアフリカの笛と太鼓と同じ鼓動だ。オサー・ターナーは2003年に95歳で亡くなった。
伝説のファイフ奏者オサー・ターナーとコーリー・ハリス
サン・ハウスの貴重な映像

●商品の購入はこちらから
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから
*参考・引用/『ザ・ブルース』(マーティン・スコセッシ監修/ピーター・ギュラルニック他編/奥田祐士訳/白夜書房)
*このコラムは2016年12月に公開されたものを更新しました。
(『THE BLUES』シリーズはこちらでお読みください)
『フィール・ライク・ゴーイング・ホーム』(Feel Like Going Home/マーティン・スコセッシ監督)
『ソウル・オブ・マン』(The Soul Of A Man/ヴィム・ヴェンダーズ監督)
『ロード・トゥ・メンフィス』(The Road To Memphis/リチャード・ピアース監督)
『デビルズ・ファイヤー』(Warming By The Devil’s Fire/チャールズ・バーネット監督)
『ゴッドファーザー&サン』(The Godfathers And Sons/マーク・レヴィン監督)
『レッド、ホワイト&ブルース』(Red, White & Blues/マイク・フィギス監督)
『ピアノ・ブルース』(Piano Blues/クリント・イーストウッド監督)
評論はしない。大切な人に好きな映画について話したい。この機会にぜひお読みください!
名作映画の“あの場面”で流れる“あの曲”を発掘する『TAP the SCENE』のバックナンバーはこちらから
【執筆者の紹介】
■中野充浩のプロフィール
https://www.wildflowers.jp/profile/
http://www.tapthepop.net/author/nakano
■仕事の依頼・相談、取材・出演に関するお問い合わせ
https://www.wildflowers.jp/contact/